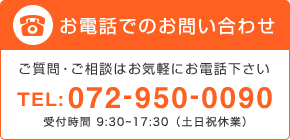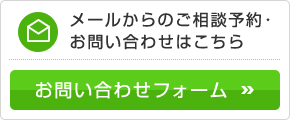改正相続法(遺産分割前の預金の払戻しを巡る諸問題)
はじめに
2019年7月1日から遺産分割関係の改正民法が施行されている。
これから数回に分けて、改正相続法のうち実務上重要なポイントを、設例をもとに明らかにしていきたい。
今回は、比較的問題となりやすい遺産分割前の預金の払戻しに関係するポイントについて述べる。
設例
被相続人は、死亡当時、甲銀行に1500万円の預金を有していた。相続人は、A、B、Cの3人の子である。3人の法定相続分は、各3分の1ずつ(=500万円ずつ)である。
- 被相続人の葬儀の喪主はAであるが、Aは被相続人の葬儀等の費用のために、遺産分割の協議が整う前に、被相続人名義の預金を引き出す手段はあるか。
- 相続人のうちBが、遺産分割をする前に被相続人の預金1500万円を全額引き出してしまった。この場合、Aは遺産を取り戻すためにどのような手段を取ることができるか。
設例1のケース
従前の取扱い
-
遺産は分割によって帰属を決する
被相続人の遺産は、相続人間で分割に関する協議を行って分割することとなる。例えば、遺産として土地、宝石類、保険等があれば、協議により各遺産の帰属を決し、価値に差があれば金銭による代償分割を行う(あるいは売却して売却代金を分割する)、ということとなる。
-
預貯金債権は例外
ただし、預金債権については、被相続人の死亡と同時に、相続分に応じて当然に分割されるものとされ、原則として遺産分割の対象とならない、とされてきた(昭和29年4月8日最高裁判決)。この最高裁判決によると、上記設例のケースでは、被相続人の死亡の時点で1500万円の預金が相続人A、B、Cに分割され、遺産分割を経ずに各自が金融機関に対して500万円ずつの債権を有する、ということとなる。
ところが、実際には金融機関は各自が分割して払戻しを受ける手続を認めていないことが多く、金融機関を相手に自らの相続分の払戻しを求める訴訟を提起する等の必要があった。そのようなこともあり、実際には預金等も遺産分割手続の中で分割協議の対象とすることが一般的に行われてきた。 -
平成28年12月19日最高裁判決
そのような中、最高裁は上記昭和29年判例を変更し、預金債権は可分債権ではなく相続人間の「準共有」になるとして、遺産分割の対象となるものと判断した。すなわち、預金債権は遺産分割を経ずに相続分に応じて当然に分割されるものではなく、遺産分割を経て分割しなければならない、ということになった。
-
実務上の問題
平成28年12月19日最高裁判決を前提とすると、預金債権は、遺産分割を経なければたとえ一部分であったとしても引き出すことはできない。そうすると、特に相続人間に争いがある場合、遺産分割の協議は長期間を要することとなり、その間預金を引き出すことが一切できない、ということとなる。しかし、例えば被相続人の葬儀費用等で被相続人の預金の払戻しを早期にうける必要があるような場合に問題が生じる。
相続法改正後の取扱い
遺産分割前の預貯金払い戻し制度の創設
まず、改正民法は、遺産である預金債権について、遺産分割の対象である(=準共有)であることを前提としつつ、一部預金について各相続人が単独で払戻しができる制度を新設した。
改正後民法909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生活費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
ポイント
- 単独で行使できる金額は、①預貯金債権のうち3分の1に法定相続分を乗じた額、②法務省令で定める額を上限(法務省令では150万円と定められた)のうち、少ない方の額
- 裁判所を通さずに(裁判所の許可等を得ずに)、各自が単独で金融機関から払戻しを受けられるものとした。
- 払戻しを受けた金額については、一部分割がなされたものとみなされる。
設例のケース
本件では、甲銀行に対する預貯金債権のうち3分の1は500万円、これにAの法定相続分3分の1を乗じた金額は約166万円となる。これは、法務省令で定める上限額150万円を上回るので、結局、Aは甲銀行から150万円の払戻しを受けることができることになる。
遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分の拡大
家事事件手続法200条3項
前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法466条の5第1項に規定する預貯金債権をいう)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部または一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
改正前の状況
本改正前でも、家事事件手続法200条では、遺産の分割の審判を本案とする保全処分を認めていた。
しかし、これは将来的な強制執行の保全、又は事件関係人の急迫の危険を防止するために必要がある場合にのみ認められるものであり、特に資金の必要性からの保全は、「急迫の危険」という厳格な要件を満たす必要があった。
そこで、実際上の必要から、(909条の2の払戻し制度とは異なり裁判所が判断することを前提として)より緩やかな要件で遺産分割前の預金債権の取得を認める法改正がなされた。
(参考200条2項)
家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
ポイント
- 要件
①遺産の分割の審判又は調停の申立てがあること
②相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があること(必要性)
③「他の共同相続人の利益を害するとき」に当たらないこと - ②の必要性については、条文に列挙されている「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁」は例示でありこれに限られない。必要性の判断については、家庭裁判所の裁量に委ねられる。
- ③の要件は、個別具体的な事情によるものとされているが、一般に、預貯金債権については当該預貯金債権の額に申立人の法定相続分を乗じた範囲内に限定されることが多いであろう(東京家庭裁判所家事第5部編著「東京家庭裁判所家事第5部における相続法改正を踏まえた新たな実務運用」)。
- 効果
「仮に取得させることができる」
もっとも、終局的な決定ではなく、民事訴訟における仮地位仮処分と本案訴訟との関係と同様、「仮に取得」した後、本案の遺産分割において当該預貯金に関しても遺産分割の調停又は審判がなされることとなる。
設例のケース
本件では、必要性がある場合には、法定相続分である500万円の範囲内で仮に取得することができる場合がある。
設例2について
問題の所在
最高裁平成28年12月19日判決は、預貯金も遺産分割の対象に含めることとした。ところが、遺産分割は、遺産分割時に存在する財産を対象とする。そうすると、相続時(被相続人の死亡時)には存在したがその後一部相続人により引き出された預金は、遺産分割時には存在しないから、遺産分割の対象とならない。この場合、他の相続人は、預金を引き出した相続人を被告として、自己の相続分相当額について、不法行為又は不当利得を原因として訴訟を提起する必要があった。
改正法は、訴訟提起ではなく遺産分割調停又は審判により解決する方法を新たに創設した。
改正法
改正民法906条の2
- 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
- 前項の規定にかかわらず、共同相続人の1人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
ポイント
- 遺産分割前に遺産が処分された場合であっても、相続人全員の同意がある場合には、遺産分割の対象とすることができる(1項)。
しかし、相続人の中の一部の者が遺産を勝手に処分した場合、その者の同意を得ることは困難な場合が多い。そこで、遺産を処分した者の同意は不要であり、それ以外の相続人の同意があれば、遺産分割の対象とすることができる(2項)。 - この法改正は方法の選択を広げる趣旨であり、従前どおり不法行為又は不当利得を原因とする訴訟を提起することも可能である。
- 処分された財産は「遺産」でなければならず、相続時(被相続人の死亡時)に存在しなければならない。例えば、相続人の一部が被相続人の生前、その意思によらずして被相続人の財産を処分した場合、遺産分割調停・審判の対象とはならない。
この場合、(理論的には)被相続人が生前Bに対して有した不法行為又は不当利得に基づく請求権を、法定相続分に応じて分割取得したとして、訴訟において不法行為又は不当利得に基づく請求をすることとなる。
本件の場合
本件では、AはCの同意さえ得ればBが遺産分割前に処分した預金についても遺産分割の対象とすることができるので、遺産分割の調停(審判)を申し立てればよい。
また、従前どおり、訴訟において不法行為又は不当利得に基づく請求をすることもできる。