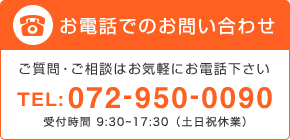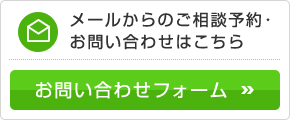不動産の財産分与において妻側の居住権を保護した裁判例
1 はじめに
夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に形成した財産を清算することを財産分与といいます。
財産分与の対象となる財産は、預金のほか、有価証券、不動産等、あらゆる種類の財産であり、資産の種類は問われません。
財産分与において特に問題となるのは、居住用の不動産についてです。
2 一般的な居住用不動産の財産分与
一般に、住宅ローン付きの不動産の財産分与を行う場合、不動産の評価額から住宅ローンを差し引いた額が清算の対象となります。
例えば、不動産の評価額が3000万円、住宅ローン残額が2000万円の場合、不動産の評価額3000万円から住宅ローン残額2000万円を差し引いた1000万円が財産分与の対象となり、通常これを2分の1ずつ(500万円ずつ)分けます(ただし、不動産購入時にどちらかが頭金としてまとまった金額を負担していた場合や、結婚前にどちらかが既に住宅ローンを組んでいたなどの場合には、分与割合が異なります)。
具体的な分与の方法としては、①売却して売却代金を2分の1ずつ分ける、②どちらか一方が不動産を取得し、他方に対して代償金(500万円)を支払う、というのが通常です。
他方で、住宅ローンの残高が評価額を上回る場合(評価額が2000万円、住宅ローン残高が3000万円の場合)、プラス財産は存在しないことになるので、財産分与の対象としないのが一般的です(東京高裁平成10年3月13日判決など)。
3 収入の少ない妻の生活権の保護
例えば、夫が会社員で妻が専業主婦、夫の名義で住宅を購入して子供と一緒に生活していたようなケースで、その後に離婚をして妻が子供の親権者となった場合、離婚後に妻が新たに住宅を借りて生活したとしても、収入が少なく生活に困窮することは少なくありません。このように離婚後に妻側が困窮するケースにおいて、例外的に妻側に居住不動産の使用継続を認めた裁判例があります。
⑴ 扶養や慰謝料を加味して妻側に不動産を取得させたケース
財産分与は通常、離婚時に存在する財産を清算するという性質を有するものですが、離婚後の妻や子の扶養や慰謝料の要素などを加味し、妻に居住不動産の所有権そのものを取得させた裁判例として、以下のものがあります。
- 夫が半身不随となった妻を置き去りにし、長期間生活費も送金しなかったケースで、財産形成に対する妻の寄与、離婚後扶養、慰謝料等一切の事情を考慮して、土地・建物全部を妻に分与することを認めたもの(浦和地裁昭和60年11月29日判決)
- 約5年の家庭内別居後の離婚のケースで、妻の年収が少なく他に居住用不動産を取得または賃借することが困難であること、病気のある子が当面同じ家に居住できるのが望ましいことから、妻に不動産を取得させ、夫に株式と預金を取得させたもの(東京地裁平成9年6月24日判決)
上記の例から分かるように、妻や子の特殊な病気のほか、夫側の帰責性が極めて大きいことなどが存在する場合に限定的に認められうるものであり、実際上は所有権まで取得できるようなケースは稀であると言わざるを得ません。
⑵ 利用権を設定したケース
⑴とは異なり、夫が住宅の所有権を取得するものの、妻に賃借権や使用権を設定することにより居住の継続を認める方法です。通常、賃貸借契約や使用貸借契約は、当事者双方の合意によって成立するものですが、以下の裁判例は、裁判所が判決や審判によって賃借権、使用借権を認めたもので、これも特殊なケースです。
- 夫名義の建物について、夫には離婚後建物に居住する意思がないことなどから、妻の賃借権の設定、賃借権の内容を判決主文に明記し、夫に賃借権設定の登記手続を命じたもの(浦和地裁昭和59年11月27日判決)
- 財産分与申立事件の抗告審において、裁判所による事実上の和解勧告により当事者に合意が成立したことから、その合意内容に沿って原審判を変更し、期限を約9年後とする使用借権を設定したもの(東京高裁昭和63年12月22日)
- 清算的財産分与として妻の持分を夫に分与したうえで、扶養的財産分与として期間を第3子が小学校を卒業するまでとする妻の使用借権を設定したもの(名古屋高裁平成18年5月31日決定)
- 財産分与後のマンションの夫の持分(約9割)につき、妻の賃借権(賃料4万6148円)を設定したもの(名古屋高裁平成27年5月28日判決)
4 まとめ
以上のように、困窮した妻側の居住権を保護した裁判例はこれまであまり多くは見られません。しかし、妻側に婚姻期間中の年金の分割を認めた平成19年法改正等、経済的弱者である妻側の保護の必要性は社会的にも認知されており、司法においても積極的な判断が求められると思われます。
(参考文献)有斐閣「離婚判例ガイド」第3版