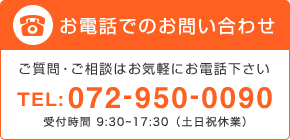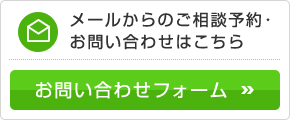振り込め詐欺における「共謀」(無罪となった2つの事例をもとに)
はじめに
いわゆる「振り込め詐欺」は近年巧妙化しており、被害者に電話を架ける「架け子」、お金を受け取る「受け子」、口座に振り込まれたお金を出勤する「出し子」など、役割が細分化している。
実務上、「架け子」、「受け子」を問わず振り込め詐欺に関与していた者は「共謀共同正犯」として詐欺罪で起訴されるのが一般的であるが、被害者が警察とともに騙されたふりをして犯人(受け子)の検挙を行ったというケースで、無罪を言い渡した下級審判例がいくつか出された。
振り込め詐欺の首謀者や実行行為者はともかく、事情を知らないまま詐欺グループに利用され犯罪に関与するケースがある。末端の役割分担者が共同正犯としての罪責を負うのはどのような場合か、検討する。
福岡地裁判決(平成28年9月12日判決)
事案の概要
- 平成26年3月中旬、X(氏名不詳者)が、V(被害者)に対して電話を行い、お金を支払うように要求。
- 3月21日、Vは詐欺に気付き、警察に相談。しかし、犯人検挙のために「騙されたふり」をすることに。
- 3月24日、Xからの電話に対し、Vは騙されたふりをし、お金の送付先を聞き出す。Vは現金を入れないまま、Xから指定されたとおり宅配便を発送する。
- 3月25日、宅配便の配達人を装った警察官がお金の送付先の住所に赴き、出てきた被告人を逮捕(なお、被告人には「受け取った荷物が詐欺の被害金かもしれないという程度の認識はあった」と認定されている)。
- 被告人は本件と同様に荷物を受け取るだけで報酬を受け取ったことが数回あった。
裁判所の判断
- 被害者が警察に相談した3月21日の段階で、被害者は騙されたことに気付いているから、それ以降、Xの詐欺行為は客観的に既遂に至る危険性は消失している。
- Xが被告人に荷物の受け取りを依頼したのは3月24日であり、被告人は既に危険性の消失したXの詐欺行為に加担したに過ぎず、その時点でXとYが共謀したとしても、詐欺の共謀にはあたらない。
名古屋高裁判決(平成28年9月21日)
事案の概要(福岡地裁とほぼ同様の事案)
- 平成27年8月、X(氏名不詳者)V(被害者)に対して息子を装って電話をかけ、現金300万円を被告人宅に送るように要求。
- 被害者は電話を受けた段階で騙されているということに気付き、警察に相談。
- 被害者が偽物の現金が入った荷物を送る。被告人が荷物を受け取った段階で逮捕
1審判決(名古屋地裁)
被害者が詐欺と気付いた時点で犯罪の危険性は消失しており、犯罪は成立しない(福岡地裁判決と同様の判断)
2審判決(名古屋高裁)
「被告に現金の受け取りを依頼した段階で、共犯の男には現金を受け取る意思があったと認められる。両者に共謀があれば詐欺未遂罪が成立する余地はある」との判断を示した。その上で、詐欺の共謀があったという証拠はないと認定。
検討
詐欺罪の成立
詐欺罪は、①欺罔行為によって②相手方を錯誤に陥らせ、③その錯誤に基づいて財産の処分行為を行わせ、④財物を取得することによって成立するものである。すなわち、①欺罔行為→②錯誤→③処分行為→④財物の取得、の各段階が因果の流れによって結びついている必要がある。
実行行為(①の欺罔行為)が行われたが、②、③、④の過程に因果関係がない場合、理論的には詐欺未遂罪が成立する。これは、欺罔行為が行われたが錯誤に陥る(騙される)ことがなかったため、財物の交付がなされなかった場合だけでなく、騙されたふりをして財物を交付した場合も含まれる。したがって、本件が単独犯として行われた場合、詐欺未遂罪が成立する。
共犯の場合
問題は、共犯の場合である。
前提として、実行行為を行っていない者が正犯者として処罰されるためには、実行行為を含む犯罪全体について「共謀」がある必要がある。これを共謀共同正犯という。
共謀は、実行行為が行われる前(事前共謀)あるいは実行行為と同時に(現場共謀)なされるのが通常である。
では、実行行為(本件では電話を架ける行為)がなされた後に共謀が行われた場合、犯罪全体について共謀共同正犯が成立するか。
まず、本件とは別に、客観的に犯罪が既遂であった場合、すなわち、欺罔行為(実行行為)がなされ、かつ、被害者が錯誤に陥り、それに基づいて処分行為がなされ、財物を取得した場合について考えてみる。
共犯者が関与したのは、実行行為がなされた後であり、実行行為自体は先行者が行っている。後行者は実行行為には何ら関与しておらず、実行行為に何らの影響も与えていないにもかかわらず、実行行為も含む犯罪全体について罪責を問うことはできない。このように考えて、犯罪全体について正犯としての罪責を問うことはできないとする見解が有力説である。
もっとも、先行者の実行行為及びこれによって生じた結果を積極的に利用する意思のもとに利用した場合、犯罪全体について正犯としての罪責を問い得る、という見解が多数説である。大阪高裁昭和62年7月10日判決(高集40・3・720)などはこの見解に立っている。
最高裁の見解は犯罪類型により同一ではなく、必ずしも明らかではない。強盗目的で被害者を殺害した夫(先行者)から、事情を知らされて金員の強取に協力を求められた妻(後行者)がこれを承諾し、ろうそくを掲げるなどして夫の強取を容易にしたという事案において、単に強盗罪・窃盗罪の幇助に留まるものではなく、強盗殺人罪の幇助が成立する、とした判決が過去に存在したが(大審院昭和13年11月18日)、最高裁でこのような見解が一般的に取られているわけではない。
では、実行行為が行われたが未遂であった場合に、実行行為後に共謀を行い犯行に加担した場合には、未遂罪の罪責(実行行為に対する罪責)を負うか。
この点に関しては、上記有力説・多数説のいずれの見解に立ったとしても、後行者に実行行為に対する罪責を問うことはできないであろう。後行者は実行行為には何ら関与しておらず、実行行為に何らの影響も与えていないし、犯罪が未遂である以上は、先行者の実行行為及びを積極的に利用する、という事態が観念できないからである。
そうすると、詐欺未遂の事案において、実行行為がなされた後に共謀がなされた場合には、正犯者としての刑事責任を問うことはできない、ということになる。
2つの判決の理解と問題点
上記福岡地裁判決(及び名古屋の一審判決)は、以上のような理屈で無罪を導いたものと思われる。
福岡地裁判決は、共謀の成立時期について、実行行為がなされた後(「架け子」が電話を架けた後)であることを前提としている。
他方、名古屋高裁判決が未遂罪の成立の余地を残しているのは、事前共謀、すなわち、実行行為前に共謀がなされたと認定しうる余地があるためだと思われる。実行行為前に共謀が成立していれば、実行行為自体にも因果的影響を及ぼしたといえ、実行行為に対する罪責を問うことは可能である(ただし、結論としては、事前共謀を認定しうるだけの証拠がない、という判断になっている)。
上記各判決の帰結をまとめると、①実行行為終了後に共謀がなされた場合は犯罪が成立しない(よって無罪)、②実行行為以前に共謀がなされた場合には犯罪が成立しうる、ということになる。このような理解を前提とすると、福岡地裁判決、名古屋高裁判決は矛盾するものではないこととなる。
通常、起訴状においては、共謀の時期は明らかにされないが、上記のように、共謀の成立時期如何によって犯罪の成否が異なることになるので、公判手続においては検察官から共謀の成立時期(少なくとも事前共謀か事後共謀か)について釈明がなされる必要がある。
なお、上記2つの判決を見ると、福岡地裁判決は共謀の成立時期としては事後共謀のみを問題とする争点整理がなされたのに対し、名古屋高裁の判決は事前共謀と事後共謀の両方を争点としていると思われるが、このあたりの事情は判然としない。
前者は実体審判を行わず公訴棄却の決定(339条1項2号)で公判手続を終わらせる余地があると思われるし、後者については共謀の成立時期に関する検察官の主張をどちらか一方に絞らせるべきではなかったかという疑問がないわけではない。
事前共謀の成否
ともあれ、これらの判決を前提とすると、事後共謀で正犯としての罪責を問うことは難しく、事前共謀の成否のみが争点となると考えられる。
問題は、振り込め詐欺などの特殊詐欺事件において、どのような場合に事前共謀が認定されるか、ということである。
共謀共同正犯における「共謀」は、明示的に行うだけでなく、黙示の共謀も含まれる。また、実行行為者と直接面と向かって謀議を行うだけでなく、間に人を介して共謀を行う順次共謀も認められる。
近年の役割が細分化された特殊詐欺事件においては、荷物の受け取りだけを行う「受け子」と言われる者、あるいはお金の出金だけを行う「出し子」と言われる者が、実行行為者である「架け子」との間で、直接、明示的に共謀を行うことは稀であると思われる。
そうすると、立証としては黙示の共謀にならざるを得ない。しかしながら、この場合においても、必ず実行行為者との間での共謀が必要であることには注意が必要である。
振り込め詐欺等の特殊詐欺事件の特徴は、本件のように「受け子」と言われる者が逮捕されやすく、「受け子」に荷物の受け取りを依頼した者や、実際に実行行為を行った「架け子」、あるいは犯罪全体を計画した首謀者は逮捕が困難であることである。
そのため、「受け子」などで逮捕された被告人は、「氏名不詳者と共謀の上・・・氏名不詳者が被害者を欺き、財物を取得した」とされ、被告人の共謀相手とされる者も、実行行為者も「氏名不詳者」とされることが多い。そして、共謀を行った相手とされる「氏名不詳者」と、実行行為者である「氏名不詳者」が通常は別人物である。
とすれば、被告人が、直接接触をした「氏名不詳者」ではなく、実行行為者である「氏名不詳者」との間で(順次)共謀を行った、との事実が主張・立証されなければならない。すなわち、単に被告人と直接接触した「氏名不詳者」とのやりとりだけではなく、その「氏名不詳者」と実行行為者である「氏名不詳者」とのやりとりについても、積極的に明示・争点化される必要がある。
黙示の共謀
次に、黙示の共謀がどのような場合に認められるかである。
振り込め詐欺のような特殊詐欺における役割分担をどのように理解するかが問題となる。
検察官は、「架け子」や「出し子」などの役割を分担して行う特殊詐欺グループであれば、各役割の者は詐欺行為についての共謀を有している、と捉えているようである。しかし、これは実態とかけ離れた理解であると指摘しなければならない。
組織的な特殊詐欺事件は、首謀者であるトップ、あるいは中核に位置するごく少人数の者によって、細分化された役割分担も含めた犯罪全体が計画・立案される。つまり、犯罪の全体像を把握しているのは、中心となる一部の者だけであり、末端の者は犯罪の計画・立案に関与していないばかりか、全体の計画を知らされることすらない。むしろ、末端の者が犯罪の計画を知ることとなると犯罪発覚のリスクが高まるため、首謀者は、末端の者に対しては、犯罪への関与を決して悟られないように、巧妙に各役割分担者への誘引を行うのである。
実際、「出し子」、「受け子」といった者は、首謀者らによって掲載された求人情報等に対して、アルバイト等の申込みを行うことによって行為に及ぶことが多い。「出し子」等の者に具体的に指示を行う者も、犯罪の一部であることを悟られないように言葉巧みに各行為を行わせる。
このような実態を前提とすれば、役割を細分化して行われる振込め詐欺などの特殊詐欺であるという事実は、むしろ、末端の者にとっては犯罪全体への共謀の存在を否定する事情になるというべきである。
詐欺の故意と「共謀」
犯罪の成立要件である「故意」も「共謀」も、いずれも犯罪の主観的要件として共通しており、「受け子」あるいは「出し子」とされる被告人側に詐欺の故意が認められれば、その事実は黙示の共謀を肯定する方向に働く。
ただ、詐欺の確定的認識があった場合と、未必的認識があったに過ぎない場合とでは、やはり黙示の共謀の推認の程度には差異が生じるであろう。
「受け子」である被告人に関して、以下のように判断した裁判例がある(東京高裁平成23年8月9日)。
「・・・検察官の主張するような認識、すなわち、紹介された仕事が違法な仕事であると認識していたことや振り込め詐欺ないしオレオレ詐欺が重大な社会問題になっていることを知っていたことから、被告人が詐欺の故意を有していたと推認することにも飛躍がある。」
上記福岡地裁判決でも、被告人には「受け取った荷物が詐欺の被害金かもしれないという程度の認識はあった」旨、認定されているが、この程度の事実をもって詐欺の故意があったと推認することもできないと考えられる(なお、本件訴訟では黙示の事前共謀の存在は争点とされていないと思われることは既に述べた)。
「出し子」、「受け子」といった者は何ら実行行為を行っていないのであって、もっぱら「共謀」のみを根拠に実行行為と結び付けられ、正犯者としての罪責を問擬されているに過ぎない。しかも、通常「共謀」が明示的に行われることはなく、唯一、黙示の共謀の存否が問われる。
公判においては、被告人の防御のためには、黙示の共謀を基礎づける事実、及び当該事実が何故に黙示の共謀に結びつくのかが明確される必要があるし、黙示の共謀の推認は慎重になされなければならないであろう。