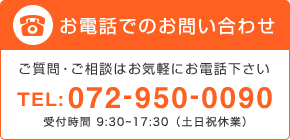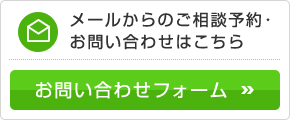将来の給付の訴えの適否を判断した事例(最高裁平成28年12月8日)
事案の概要
本件は、上告人である日本国が、日米安全保障条約等に基づき、アメリカ海軍に対して自衛隊の厚木海軍飛行場を使用させたのに対して、同飛行場周辺に居住する被上告人らが、同飛行場において離着陸するアメリカ海軍及び自衛隊の航空機の発する騒音等により精神的・身体的損害を被っているとして、①人格権に基づく離着陸等の差し止め及び音量規制を請求するとともに、②国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を請求した。
争点
原審の口頭弁論終結後平成28年12月31日までに発生すべき損害(将来発生すべき損害)の可否
争点に対する原判決の判断
原審 東京高裁平成27年7月30日(平成26年(ネ)第4072号)
「平成29年頃にアメリカ海軍において航空機の配備状況の変動が見込まれるところ、原審の口頭弁論終結の日の翌日から平成28年12月31日までの期間については、原審の口頭弁論終結時点における厚木海軍飛行場の周辺地域の航空機騒音の発生等が継続することが高度の蓋然性をもって認められ、上告人に有利な影響を及ぼすような将来における事情の変動を理由とする請求異議訴訟においてその事情の変動の立証負担を上告人(国)に課することが格別不当ということはできない」として、将来の給付部分について認容。
最高裁判所の判断
最高裁は、原審の判断は誤りであるとして、請求を棄却した。
「継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求権については,たとえ同一態様の行為が将来も継続されることが予測される場合であっても,損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず,具体的に請求権が成立したとされる時点において初めてこれを認定することができ,かつ,その場合における権利の成立要件の具備については債権者においてこれを立証すべきであり,事情の変動を専ら債務者の立証すべき新たな権利成立阻却事由の発生としてとらえてその負担を債務者に課するのは不当であると考えられるようなものは,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものと解するのが相当」
「そして,飛行場等において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分については,将来それが具体的に成立したとされる時点の事実関係に基づきその成立の有無及び内容を判断すべきであり,かつ,その成立要件の具備については請求者においてその立証の責任を負うべき性質のもの」
よって、このような請求権が将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない。
コメント
民事訴訟における給付の訴えは、原則として既に発生している過去の請求権について認められるものである。将来発生すべき請求権については、例外的に、「あらかじめその請求をする必要がある場合限り、提起することができる」とされている(民事訴訟法135条)。
この「あらかじめその請求をする必要がある場合」の意義については、最高裁の過去の判例により、3つの要件を満たす場合とされている。すなわち、①当該請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されること、②当該請求権の成否及びその内容につき債務者に有利に働く事情の変動があらかじめ明確に予測しうる事由に限られること、③この事情の変動について請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても格別不当とは言えないこと、の3要件を満たされる場合に肯定されるとしている(最高裁昭和56年12月16日(大阪国際空港事件))。
将来発生すべき損害賠償請求が肯定される典型例は、不法占拠者に対する明渡請求とともに、明け渡しまでの賃料相当損害金の賠償を請求するケースである。これは、①請求の基礎となる事実関係は「不法占拠」の事実であるところ、口頭弁論終結前の不法占拠状態の継続があれば事実関係の流動性はなくその継続が予測される、②債務者に有利に働く事情の変動は「占有状態の解消」又は「占有権限の取得」という明確に予測しうるものに限られる、③占有状態の解消や占有権限の取得といった事情は比較的容易に立証できる反面、長期間不法占有状態が継続していたという事情に鑑みれば、執行阻止責任を債務者側に課しても格別不当とは言えない、ということとなる。
しかし、とりわけ国家の安全保障上の理由で使用されている飛行場の場合、航空機の離発着の継続が予想される場合であっても、騒音の状況はその時々の安全保障状況、航空機の配備態勢、天候等不確定な事情によって常に変動する可能性を有するのであり、離発着が不法行為となるか否かや、賠償の範囲などの点については流動性を持つ事実関係の展開という法的評価に左右されざるを得ない。
そうすると、たとえ航空機の離発着の継続が予測されるものであったとしても、不法行為の成否やその額をあらかじめ一義的に明確に決定することは困難であると言わざるを得ず、賃料相当損害金の場合と異なり、賠償の適格性はないものと言うべきである。
今回の最高裁判決は、従前の最高裁の立場からすると当然の結果であり妥当な判断であろう。